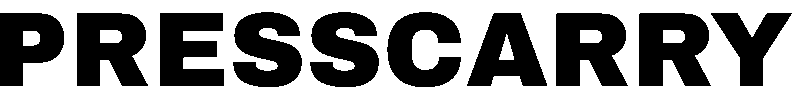7月31日、住吉大社にて夏の伝統行事である夏越祓神事が執り行われました。
この神事は、住吉祭の中心となる儀式で、暑さが増す季節に心身を清めるための古くからの習わしです。
夏越祓神事は、半年間の罪や穢れを祓い、疫病が蔓延しやすい夏を無事に過ごすことを願うための行事で、住吉大神がミソギ・ハラエを司る神であることから、例祭は大祓と共に実施されます。古くは旧暦の6月末日に行われていましたが、現在は新暦に合わせて7月31日を祭日としています。
神事では、まず「夏越女」をはじめとする奉仕者が、非公開の儀式である「粉黛戴盃式(ふんたいたいはいしき)」で奉仕資格を得た後、装束をまとった奉仕者が「茅の輪(ちのわ)」をくぐり、罪や穢れを祓い清めます。
この茅の輪くぐりの行列は、江戸時代後期に一度途絶えましたが、昭和4年(1929年)に再興されました。
現在はこの伝統を、住之江区御崎地区を中心とした夏越女保存会が引き継いでいます。
夏越祓神事当日の様子