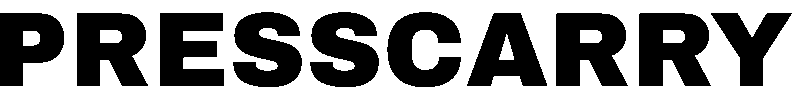日本の芸術教育の最高峰である東京藝術大学は、2026年から3年連続でシリーズ開催される『藝大式 美術の“ミカタ”―この夏、藝大生になる―』の第一弾となる2026年の展覧会開催を決定しました。本展覧会は、東京藝術大学が培ってきた芸術教育の知見を広く一般に提供し、来場者が「藝大生」として美術の奥深さを体験できる機会となります。
展覧会『藝大式 美術の“ミカタ”』の概要
本展覧会は、東京藝術大学ならではの視点と方法で「美術の見方」を教える、新たな体験型展覧会として開催されます。
開催概要
* 展覧会名: 藝大式 美術の“ミカタ”―この夏、藝大生になる―
* 会期: 2026年7月24日(金)~9月23日(水・祝)※予定
* 会場: 東京藝術大学大学美術館 本館 展示室1、2、3、4
* [所在地] 〒110-0007 東京都台東区上野公園12-8
* 主催: 東京藝術大学、読売新聞社
* お問い合わせ: 050-5541-8600(ハローダイヤル)
* 東京藝術大学大学美術館公式サイト: https://museum.geidai.ac.jp
* ※展覧会公式サイトは現在準備中。詳細は決定次第、公式サイト等で告知されます。

体験型展覧会開催の背景
東京藝術大学は、その独特な教育環境や学生の日常が広く知られていますが、具体的な学びの内容は一般に謎に包まれていました。今回、東京藝術大学が「初めての試み」として「講義形式」の「体験型展覧会」を開催する背景には、長年培ってきた芸術教育の知見をより多くの人々に届けたいという強い思いがあります。本展覧会は、実際に美術を学ぶ一歩を踏み出す貴重な機会となります。
展覧会の主な特徴
本展覧会には、以下の注目すべき特徴があります。
1. 3年連続シリーズ企画による「美術のミカタ」の深掘り
2026年から2028年まで、毎夏に開催されるシリーズ企画として展開されます。一度きりのイベントではなく、継続的に美術に対する理解を深める機会を提供し、毎年異なるテーマで多角的に美術を学べることが期待されます。
2. 現役教授・講師陣が企画する「講義形式」の展示
美術作品を単に鑑賞するだけでなく、現役の先生方が企画した「講義」として鑑賞できます。専門家ならではの視点や知識を通して、作品の背景にある歴史、技術、思想といった深い層まで理解を深めることが可能です。
3. 多角的なアプローチで美術を学ぶ
今回の第一回目では、東京藝大の豊富なコレクションを中心に、以下の幅広いテーマで美術にアプローチします。
- 美術の歴史: 作品が生まれた時代背景や流れを学びます。
- 実技・表現: どのように作品が制作されたのか、その技術とプロセスに迫ります。
- 鑑賞: 作品と向き合い、来場者それぞれの「ミカタ」を発見します。
- 素材: 作品を構成する素材が持つ意味や特性を探ります。
- 保存修復: 古い作品がどのように守られ、次の世代に引き継がれるのかを学びます。

特に「保存修復」というテーマは、文化財を守るための高度な技術に光を当てます。東京藝大の文化財保存学専攻が誇る専門分野であり、劣化した仏像がどのようにして輝きを取り戻すのか、そのプロセスを学ぶ貴重な体験が提供されます。
4. ワークショップ併設による参加型学習
会場には、子供から大人まで気軽に楽しめるワークショップも併設されます。座学だけでなく、体験を通じて美術の面白さを直感的に感じることができ、手を動かすことで作品を見る目が変化することが期待されます。
展示予定作品の一部紹介
本展覧会では、東京藝大が所蔵する貴重なコレクションが「教材」として展示される予定です。その一部をご紹介します。
小倉遊亀「径」1966年

小倉遊亀「径」1966年 東京藝術大学所蔵
日本画の巨匠、小倉遊亀の作品です。柔らかな色彩と独自の構図で観る者を惹きつけ、「径」は母と子、そして犬の日常の一コマを描いた温かい作品です。日本画の表現技法や、描かれた当時の社会背景、作者のメッセージを読み解く視点が提示されます。
黒田清輝「トゥルプ博士の解剖講義」(レンブラント・ファン・レイン原作)1888年

黒田清輝「トゥルプ博士の解剖講義」1888年 東京藝術大学所蔵(レンブラント・ファン・レイン原作)
西洋近代絵画の父、黒田清輝がレンブラントの名作を模写したとされる作品です。美術史における「模写」の重要性や、西洋美術が日本にどのように受容されていったのか、当時の美術教育の歴史を考えるきっかけとなるでしょう。
快慶・安阿弥「大日如来坐像」と信太司「快慶作大日如来坐像による木彫仏像技法研究」の比較
この展示は、美術の「保存」と「継承」というテーマを深く掘り下げます。
- 快慶・安阿弥「大日如来坐像」:鎌倉時代に生み出された名仏像。
- 信太司「快慶作大日如来坐像による木彫仏像技法研究」:現代の作家が、過去の巨匠の技法を研究し、再現を試みた作品。
二つの作品を比較することで、古典から現代へと繋がる芸術の「DNA」を直接感じることができます。
チケットおよび参加方法について
現時点では、チケット料金や購入方法といった具体的な情報は「準備中」とされています。東京藝術大学という場所で、これほど深く美術を学べる機会は貴重です。公式サイト等で詳細が発表され次第、すぐに確認することをお勧めします。
本展覧会の意義
東京藝術大学が総力を挙げて取り組む新しい視点の展覧会『藝大式 美術の“ミカタ”―この夏、藝大生になる―』は、単に作品を鑑賞するだけでなく、現役の先生方から「講義」を受け、ワークショップで手を動かすことで、美術の奥深さを多角的に学ぶ機会を提供します。2026年夏、上野公園の東京藝術大学大学美術館にて、来場者それぞれの「美術のミカタ」が変化する体験が期待されます。今後の詳細発表に注目が集まります。