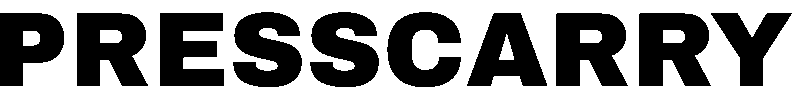株式会社日比野設計が手掛けた認定こども園「FK Kindergarten and Nursery」が、世界最大級の国際建築イベント「World Architecture Festival 2025(WAF 2025)」の完成建築・学校部門で最優秀賞を受賞しました。狭く高低差のある敷地を逆手に取り、子どもたちの成長を促す遊びと学びの空間へと昇華させた革新的なデザインが世界で高く評価されています。この受賞は、子どもたちの未来を育む建築の可能性を示しています。
WAF 2025 最優秀賞の概要
幼児施設設計の専門家集団である株式会社日比野設計は、国際建築イベント「World Architecture Festival 2025(WAF 2025)」において、完成建築・学校部門で最優秀賞を獲得しました。
WAFは「建築界のオスカー」とも称される権威ある国際アワードであり、毎年世界中から数百件もの応募があります。最終審査は「ライブ・クリティーク(公開プレゼンテーション)」形式で行われ、設計意図や社会背景、イノベーションの深さが多角的に評価されます。
今年のWAF 2025では、世界から780件を超える応募があり、日本からは日比野設計を含むわずか6社がショートリスト(最終選考)に残り、最終的に日比野設計と日建設計の2社のみが部門最優秀賞に輝きました。

FK Kindergarten and Nurseryの設計概要
最優秀賞に選ばれたのは、長崎県に建設された認定こども園「FK Kindergarten and Nursery」です。

この施設は、狭く高低差のある敷地という困難な条件を逆手に取り、既存の園舎と園庭を活かしつつ、高低差を巧みに利用した立体的で奥行きのある環境を構築しています。高低差を子どもたちが身体と頭を使う遊びの要素へと昇華させることで、単なる安全な空間に留まらず、子どもたちの成長を促す空間が実現されました。
また、敷地形状を最大限に活かすことで、土の搬出入をほとんどなくし、工事中の二酸化炭素排出削減にも貢献するなど、環境への配慮もなされています。
「FK Kindergarten and Nursery」プロジェクト概要
* 所在地: 長崎県長崎市
* 設計監理: HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro + KIDS DESIGN LABO
* 敷地面積: 2730.38m²
* 建築面積: 820.53m²
* 延床面積: 1075.25m²
* 構造規模: 木造、地上2階建
園内では、子どもたちがそれぞれの場所で活動しています。


Cheer Kindergartenの設計概要
今回の受賞に加え、中国深センに完成した幼稚園「Cheer Kindergarten」も同部門でショートリストに選出されました。

このプロジェクトでは、既存の4層吹き抜け空間を持つ建物を幼稚園として改修するにあたり、吹き抜けを塞ぐのではなく、ダイナミックな空間を活かして子どもたちが遊ぶための「鳥の巣を模したオブジェ」を配置しました。この超立体的な展開により、子どもたちの相互交流が活発化し、異年齢間のコミュニケーションが自然に促されるデザインとなっています。

「Cheer Kindergarten」プロジェクト概要
* 所在地: 中国深セン市
* 設計監理: HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro
* 敷地面積: 2743m²
* 建築面積: 1110m²
* 延床面積: 4240m²
* 構造規模: 鉄筋鉄骨コンクリート造、地下1階、地上4階建
株式会社日比野設計について
株式会社日比野設計は「幼児施設設計の専門家集団」として、子どもたちの成長と教育環境に特化したデザインを追求しています。同社は、幼児施設設計を専門とする「日比野設計+幼児の城」と、福祉施設設計を専門とする「日比野設計+福祉施設研究所」の2つの専門分野で構成されています。
2021年3月には、自社で設計・運営する保育園「KIDS SMILE LABO」をオープンし、保育環境の研究と実践を通じて得られた知見を次のデザインに活かす取り組みを行っています。保育環境の総合的なコンサルティングも手掛けており、未来の教育施設のあり方を問い続けています。
- 商号: 株式会社日比野設計
- 代表: 代表取締役会長 日比野 拓
- 設立: 1972年7月
- 本社所在地: 神奈川県厚木市飯山南四丁目18-1
- 事業内容: 建築設計監理業務、幼児施設及び福祉施設のコンサルティング
- 公式ウェブサイト: https://hibinosekkei.com/
- 幼児の城: https://e-ensha.com/
- 福祉施設研究所: https://hibino-fukushi.com/
- KIDS SMILE LABO: https://kidssmilelabo.com/
今回のWAF 2025での最優秀賞受賞は、日比野設計が長年にわたり培ってきた専門性と、子どもたちへの深い理解が世界に認められた大きな一歩です。彼らの建築は、子どもたちの身体的・精神的な成長を促し、好奇心を刺激する「生きた教材」として、未来の教育施設のあり方に新たな可能性を提示しています。