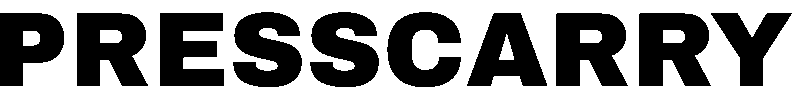提供:@Press
概要
京都大学、弘前大学、名城大学、イスラエル・ベン=グリオン大学、福島大学の研究チームは、日本の在来植物であるオオバコ(Plantago asiatica)が塩ストレスを受けた際に、地上と地下の両方を通じてストレス情報を他の個体に伝達していること、さらに情報が伝わる相手が地上部と地下部で異なることを明らかにしました(図1)。塩ストレス情報は、地下部の根を介した場合、同じ親個体由来のきょうだい個体間で伝達されやすい一方、地上部の空気(揮発性化合物など)を介した場合は、遺伝的な差異に関係なくすべてのオオバコ個体に伝わり、塩ストレスに対して有効と考えられる気孔を閉じる反応を誘発することが分かりました。これらの結果は、地上部と地下部の情報伝達がそれぞれ異なる機能をもつことで複雑な個体間の情報伝達が行われている可能性を示しています。今後は、このような情報のやりとりがオオバコの生存や成長、そして集団全体のストレス耐性にどのように影響しているのかを詳しく調べることで、植物の集団レベルでのストレス耐性機構の解明が期待されます。
本研究は、2025年8月13日に「Plant Signaling & Behavior」誌に掲載されました。

図1.研究成果の概念図
研究背景
植物は一度根付くと移動することができないため、周囲の環境を正確に読み取り、適切に反応する能力が重要です。特に、乾燥や塩分などのストレスが差し迫る状況では、ストレスを受けた隣接する植物からの様々な刺激を受けとり、あらかじめ備える予測的な応答が生存上重要になると考えられています。事実、これまでの研究でも乾燥ストレスを受けた植物は、葉や根から様々な化学物質を放出し、それらを受容した他の植物は、あらかじめ葉の気孔を閉じるなどの水分の損失を防ぐのに有効な応答を示すことで、枯死するリスクを軽減していることが知られています。しかし、地上や地下の情報伝達にはどのような機能の違いがあるのかについてはほとんど明らかにされていませんでした。
植物群落の中には、同じ種であっても遺伝的に近い個体から遠い個体まで、さまざまな遺伝的距離を持つ個体が混在して生育しています。私たちは、この同種個体間の遺伝的な違いに注目し、地上部と地下部の情報伝達を同時に評価することで、それぞれの機能の違いを探りました。
研究手法・成果
本研究では、地上部(空気)と地下部(根)での情報伝達を分離して評価できる独自の実験系を構築しました(図2)。中央のストレス誘導個体の片方の根には塩(NaCl)を与え、もう片方の根を地下部受容個体と接触させて植え付けました。ストレス誘導個体と地下部受容個体の地上部は、プラスチックプレートで仕切り、地下部の刺激のみが伝達可能な条件を設定しました。地上部受容個体は、ストレス誘導個体との間を穴の開いたプラスチックプレートで仕切ることで、揮発性成分などを介した情報伝達を可能な状態で設定しました。この条件で、ストレス誘導個体に塩ストレスを与えて60分後の地上部、地下部受容個体の葉の気孔の開閉率を計測しました。さらに、地上部および地下部の受容個体には、それぞれ異なる遺伝的距離を持つ個体(きょうだい、近隣個体群、遠方の個体群)を用いて実験を行うことで、遺伝的距離が地上部と地下部の情報伝達に与える影響を検証しました。

図2.実験デザインの概要。植物の色の違いは遺伝的な違いを示す。
その結果、塩ストレス情報はオオバコの地上と地下の両方を通じて他の個体に伝達されていること、さらに情報が伝わる相手が地上部と地下部で異なることが判明しました。具体的には、地下部を通じて伝達されるストレス情報に対しては、遺伝的距離が近い個体ほど強い反応を示し、きょうだい個体では気孔を最大で55%閉じるなど、より顕著な塩ストレス応答が見られました。一方、地上部を介した情報伝達に対しては、遺伝的な距離にかかわらず、すべての植物が同様に気孔を閉じる反応を示すことが明らかになりました(図3)。

図3.実験条件毎の開いている気孔の割合。アルファベット大文字の違いは、ストレス処理間の統計的な差異を、小文字の違いはストレス処理内の遺伝的条件間での統計的な差異を示す(P<0.05)。N.S.は統計的な差異がないことを示す。
波及効果と今後の展望
本研究により、塩ストレス情報は、地上と地下といった異なる経路を通じて同時に伝達されること、さらに地上と地下のシグナルによって伝達されやすい個体が異なることが初めて示されました。これらの結果は、植物のストレス環境への適応において、地上と地下での複雑な個体間の情報伝達が重要な役割を果たしている可能性を示しています。今後は、情報伝達を担う化学物質の特定や、このような情報のやりとりがオオバコの生存や成長、そして集団全体のストレス耐性にどのように影響しているのかを詳しく調べることで、植物の集団レベルでのストレス耐性機構の解明が期待されます。
【研究助成金】
本研究は、⽇本学術振興会(18K19353、19H03295、 22K19337、 23H02558、 23H04970)の⽀援を受けて⾏われました。
【用語の解説】
注1)塩ストレス:高塩分濃度の環境では、通常の環境に比べて植物が土壌から水を吸収しにくくなり、その結果、吸水が阻害されるか脱水状態に陥ることになります。こうした状況に対し、植物は水分損失を抑えるため、気孔を閉じる反応を示します。
【研究者のコメント】
今回の実験から、植物群落内では地上部と地下部の両方を通じて複雑な情報伝達が行われている可能性が示されました。今後は、植物同士がどのように情報をやり取りしながら、多様なストレスへの耐性を群落全体で高めているのかを解明し、植物の集団生活の実態に迫っていきたいと考えています。(京都大学 山尾 僚)
地上部と地下部で情報が伝わる相手が異なるという結果は、私たちも予想していなかった興味深い発見です。この違いはオオバコにとって、多様な環境で生き延びるための戦略のひとつである可能性があります。今後は、こうした情報伝達の仕組みがどのように生まれ、高度化してきたのかを紐解き、植物の巧みなコミュニケーション能力の進化プロセスにも迫りたいと考えています。(名城大学 大崎 晴菜)
一般に、同種の他個体は競争相手とみなされます。それにもかかわらず、一見すると競争相手を利するような現象は、なぜ進化したのでしょうか。また、地下部と地上部で情報が伝達される相手に違いがあることには、どのような適応的意義があるのでしょうか。本研究の成果はこうした疑問を提起し、複雑な生物間相互作用の解明に向けた足掛かりとなります。今後の研究の展開に是非ご期待ください。(福島大学 廣田 峻)
【論文情報】
タイトル: Integrated above- and below-ground interplant cueing of salt stress
著者: Kai Ito, Haruna Ohsaki, Ariel Novoplansky, Shun K. Hirota, Akira Yamawo
掲載誌: Plant Signaling & Behavior
DOI:10.1080/15592324.2025.2542560
URL: https://doi.org/10.1080/15592324.2025.2542560
キーワード: オオバコ、血縁認識、植物間コミュニケーション、ストレス応答、揮発性有機化合物、根放出物
【研究に関するお問い合わせ先】
京都大学生態学研究センター教授山尾僚(やまお あきら)
TEL:077-549-8235
E-mail:yamawo.aki@gmail.com
名城大学 農学部 助教 大崎 晴菜(おおさき はるな)
TEL:052-838-2433
E-mail:ohsakih@meijo-u.ac.jp
【報道に関するお問い合わせ先】
京都大学 広報室国際広報班
TEL: 075-753-5729 FAX: 075-753-2094
E-mail:comms@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
名城大学渉外部 広報課
TEL: 052-838-2006FAX: 052-833-9494
E-mail: koho@ccml.meijo-u.ac.jp
福島大学 総務課 広報・渉外室 広報係
TEL: 024-548-5190FAX: 024-548-3180
E-mail: kouho@adb.fukushima-u.ac.jp