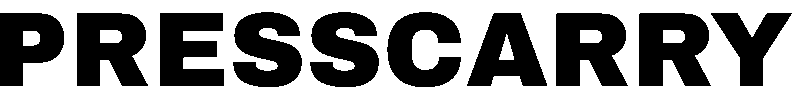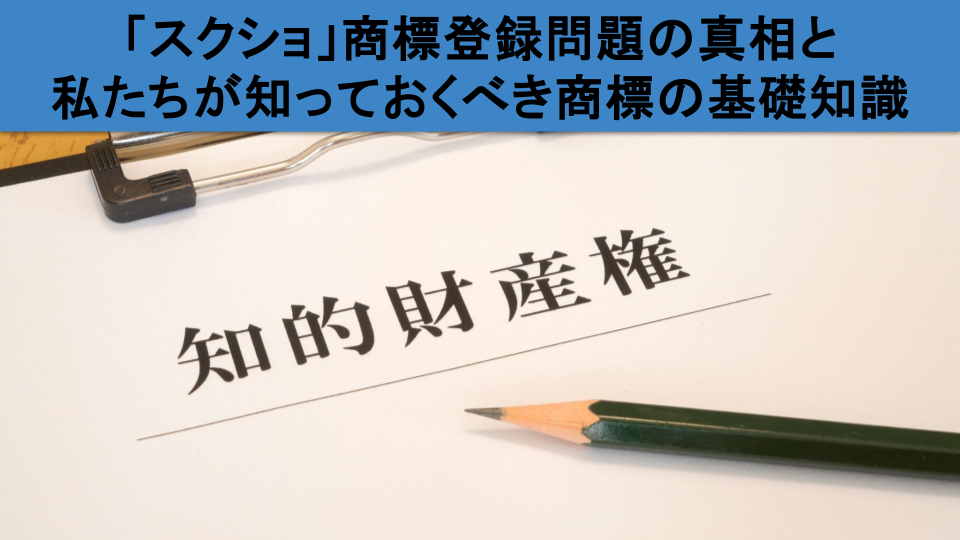
「スクショ」商標登録問題の真相と、私たちが知っておくべき商標の基礎知識

監修
弁理士法人ソシデア知的財産事務所
代表弁理士 小木 智彦
開業:2011年4月4日
先日、GMOメディア株式会社の「スクショ」の商標権がSNS上で話題になりました。この問
題を中心に、商標登録に関する様々な疑問や法律的な問題について、ソシデア知的財産事務
所の小木智彦先生にインタビューしました。
1. なぜ商標登録は必要?
大谷
企業がサービスや商品を展開する上で、商標登録はどのような意味を持つのでしょうか?改めて、その重要性について教えてください。

小木先生
商標登録は、「この名前やロゴは私のものです」ということを、特許庁を通じて国に認めてもらうもので、国ごとに登録されます。登録された名前やロゴを指定された商品やサービスで独占的に使用できるため、他人が無断で模倣したり、似たような名前やロゴを使用したりすることに対抗できます(使用差し止めや損害賠償を請求できます)。
つまり、商標登録は、その名前やロゴに関連する商品やサービスの信用とブランド価値を保護するために非常に重要なのです。
逆に言えば、商標登録をしないでおくと、他人に同じ名前を使って粗悪品を販売されたり、品質の低いサービスを提供されたりして、自分の会社の信用やブランド価値が損なわれる可能性があります。
そのため、事業を行う上で、商標登録は必要不可欠と考えます。
2. 特許庁の商標審査の基準について
大谷
2014年に、GMOメディアが「スクショ」という言葉を商標登録しようとしましたが、この頃と現在で、特許庁がよくある言葉の商標登録を認めるかどうかという基準は変わったのでしょうか?

小木先生
商標の審査は、特許庁が発行する「商標審査基準」というものに基づいて判断され、2014年から現在まで、この基準に大きな変更はありません。
しかし、最近では、インターネットですでに使われているような言葉は、審査官が慎重に判断する傾向があると感じます。
今回の「スクショ」の商標登録も、特許庁の審査では一般的な言葉として一度は登録が難しいと判断されたようですが、GMOメディアが反論した結果、登録が認められたと考えられます。
3. 使っていないと商標登録が取り消される?
大谷
商標登録後、3年間使っていない場合、登録が取り消されるというルールがありますが、「スクショ」の場合はどうなるのでしょうか?

小木先生
今回登録された商標は、「スクショ」という言葉を、第42類で指定されたサービスで使用した場合に、商標が使われたと認められます。この使用が、登録から3年以内に行われないと、他の人から「不使用取消審判」という手続きで取り消される可能性があります。
また、今回の登録商標は「標準文字」という指定があるため、標準的なフォントで「スクショ」を使用した場合に限られます。もし、特殊なフォントやデザインされた文字、英語やひらがな等で使用した場合は、使用していないとみなされる可能性があり、その場合は、他の人が不使用取消審判を起こして、この商標登録を取り消すことがでます。
GMOメディアのウェブサイトには、「当社における事業保全および将来的な活用の可能性」との記載があるため、積極的に商標を使う意図はあまり感じられず、今後、未使用で取り消される可能性は十分にあると感じられます。
4. 先願主義という制度について
大谷
現在の特許や商標の出願では、先願主義という制度が採用されていますが、この制度について、何か法改正の必要性があると思いますか?小木先生のご意見をお聞かせください。

小木先生
特許や商標の先願主義とは、先に特許庁に出願した人が権利を取得するという制度です。特許庁への出願によって、日付と内容が確定できるため、行政側が管理するには効率的な方法とされています。
しかし、この制度にはデメリットもあります。例えば、特許の場合、実際に発明したタイミングが出願した人よりも先であっても、出願しなければ、後から出願した人のほうが有利になり、争うことが難しくなります。
また、商標制度を知らない中小企業や個人商店の場合、例えば、ラーメン店の店主が商標登録をせずに、弟子がその店の名前を商標登録してしまい、店主が店の名前を変えざるを得なくなるケースもありました。したがって、先願主義の問題点を、私たち専門家が個々のケースに合わせて対応していく必要があります。
5. 他人による商標の先取り登録への対応について
大谷
過去に発生した「ゆっくり茶番劇」の商標取得のケースのように、商標登録をしていなかった個人や企業が同様の被害に遭った場合、どのような対応策が考えられるでしょうか?

小木先生
「ゆっくり茶番劇」のケースでは、結局、商標権者が主張した10万円のライセンス料の徴収は実現しなかったことを紹介します。同様に、時々、商標を使ってライセンスビジネスをしようと考える人が現れますが、どれもうまくいっていないと感じています。
もし、自分で商標登録をせずに、他人や企業が自分の名前やロゴを登録してしまった場合は、慌てずに、次の対応策を確認することを勧めています。
- 商標が同じか似ているか(フォント、ローマ字、ひらがな・カタカナ等)を確認する
- 自分が展開している商品・サービスが、その商標の指定商品・指定役務と同じかを確認する
例えば、「朝日」と「アサヒ」という商標で、登録商標に書いてある指定商品が「新聞」であれば、同じ商標であっても、指定商品が「ペンキ」であれば、権利侵害にはなりません。実際に、朝日新聞とアサヒペイントは、どちらも商標が「朝日」と「アサヒ」で似ていますが、登録商標が共存しています。
したがって、商標が同じか似ているものでなければ問題ありませんし、商標が同じか似ているものであっても、商品・サービスが指定商品・指定役務と異なる場合は、問題ありません。そして、これらの点に問題がないようであれば、他人に先に登録されないように、自分で商標登録しておくことをお勧めします。
6. 今後、商標権を取得する際に注意すること
大谷
今回の「スクショ」のようなケースを踏まえ、今後、企業や個人が商標登録を行う際に、どのような点に注意すべきでしょうか?

小木先生
企業や個人が商品やサービスを展開する際に、名前やロゴを決める際、登録商標として他人の権利となっている名前やロゴではないかを確認する必要があります。
これを怠ると、ウェブページやチラシを作成した後で、その名前やロゴを使用できなくなり、全てを書き換えることになる可能性があります。
現在、商標権者は、登録商標である名前やロゴをインターネットで検索すると、その名前やロゴを無断で使用している人(権利侵害者)を見つけ出すことができます。そして、権利侵害を知って警告してくるケースがあります。その場合、せっかく始めた名前やロゴを使用できなくなることがあります。
そのため、新しい名前やサービスを使用する際には、特許庁のウェブページ「J-PlatPat」で登録商標を調べてみるか、専門家である弁理士に相談することを勧めています。
まとめ
今回の記事では、GMOメディアの「スクショ」商標登録問題をきっかけに、商標制度の基本的な仕組みや、商標登録を行う上での注意点についてソシデア知的財産事務所の小木智彦先生に開設していただきました。
商標登録は事業を行う上では必須といえるものになります。今回の記事を参考にしていただき、各企業様の今後のご発展を願っております。
- 商標登録の審査基準は、2014年から現在まで大きく変わっていない。
- 登録後3年間使用していない商標は、取り消される可能性がある。
- 商標登録は、商品やサービスの信用とブランド価値を守るために重要である。
- 先願主義にはデメリットもあり、専門家によるサポートが必要となる場合がある。
- 他人の商標を先取り登録した場合でも、権利行使が制限されるケースがある。
- 商標登録を行う際は、事前に登録商標の調査や専門家への相談が重要である。