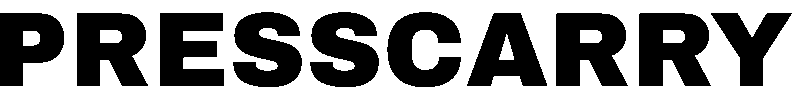提供:@Press
デザイナーの猿吉は、エレベーターにおいて長年の課題である開閉ボタンの押し間違いを根本的に解決する「絶対に間違えない開閉ボタン」を開発しました。
日常に潜むリスク – エレベーターにおける開閉ボタンの押し間違い
現代社会において、エレベーターは日常生活に欠かせない移動手段となっています。国土交通省の統計によれば、日本国内には約70万台のエレベーターが設置されており、一日あたりの利用者数は延べ数億人に上ると推計されています。
そんなエレベーターで長年人々を悩ませているのが、開閉ボタンの押し間違いです。
多くの人が、開閉ボタンの押し間違いによって、扉で人を挟んだ・扉に挟まれたという経験があるでしょう。
また、それも一度や二度ではなく、何度もあるのではないでしょうか。
この問題は、単なる不快さや不便さにとどまらない社会問題でもあります。
国土交通省の調査によると、エレベーター関連の事故のうち、扉の開閉に関するトラブルは全体の約30%を占めており、その多くがボタンの押し間違いに起因しています。
特に高齢者や子ども、障がいを持つ方々にとっては、閉まりかけのドアに挟まれることによって、重大な怪我に繋がる可能性も否定できません。
また、急いでいる時間帯や混雑した状況では、押し間違いによるストレスや人間関係のトラブルに発展することも懸念されます。
高齢化社会が進む日本においては、誰もが瞬時に直感的に認識できる開閉ボタンのデザインの重要性がますます高まっています。
なぜ同じ間違いを繰り返すのか – 現行デザインの問題点
現在広く採用されているエレベーターボタンのデザインは、主に三角形の頂点の向きで「開」と「閉」を区別する仕様となっています。
頂点が外側を向いている三角形は開く扉を、内側を向いている三角形は閉まる扉を表しています。
じっくりと見比べれば、この違いを判断することができるでしょう。
しかし、この微妙な違いを閉まりかけた扉に人が駆け込んできた際などの慌ただしい状況で瞬時に判断することは非常に困難です。
これが、押し間違いが頻繫する原因だと考えられます。
そのため、押し間違いを防ぐための改良版として「開」のボタンを緑色にするデザインも広く採用されていますが、押し間違いは解消されていません。
また、矢印を用いたデザインも存在しますが、三角形と同様に方向性の瞬時判断が必要なため、根本的な解決には至っていないのが現状です。
これらの事実は、単に色を変えたり、三角形を矢印に変えたりするだけでは不十分であり、根本的に異なる全く新しいデザインの必要性を示しています。

主な開閉ボタンのデザイン
「開を開く」- 革新的な解決策
この長年の課題を解決すべく開発されたのが「絶対に間違えない開閉ボタン」です。
このデザインの最大の特徴は、「開」の「門」の部分の間隔を広げることで、視覚的に「開く(開いた)」状態を表現している点です。
「開」という漢字自体が「開く」という意味を持っていることに着目し、その形状も「開く(開いた)状態」を表すようにデザインしました。
一方、「閉」はそのままの形状を保持することで、明確な違いを生み出しています。また、上下に「開」と「閉」を重ねて配置することで、両者の違いがより明確になり、視認性が更に向上します。
このデザインは、従来の概念を覆す画期的なデザインですが、採用している「開を開く」というコンセプトは、極めて単純です。
しかし、多くのデザイナーが見過ごしてきた盲点でした。
このデザインが優れている点は以下の通りです。
1. 言語や文化の違いを超えて、誰もが直感的に理解できる。
2. 急いでいる状況でも瞬時に適切なボタンを選択できる。
3. 色に依存しない普遍的なデザインである。

開を開く

配置①(横)

配置②(縦)
今後の展望と社会的意義
本デザインは、単にエレベーターの利便性を高めるだけでなく、より大きな社会的意義を持っています。
高齢化社会における安全性向上、バリアフリー環境の整備、そしてユニバーサルデザインの推進という観点からも、重要な一歩となります。
今後は、実用化に向けた取り組みを強化していく予定です。
また、公共施設や商業施設、医療機関など、多くの人が利用する場所への優先的な導入を目指しています。
さらに、この「絶対に間違えない開閉ボタン」のデザイン思想は、エレベーターだけでなく、様々な機器のインターフェースデザインにも応用できる可能性を秘めています。
直感的で分かりやすいデザインの重要性が増す現代社会において、このシンプルかつ革新的なアプローチは、多くのデザイン課題の解決に寄与することが期待されます。
お問い合わせ先
• 代表:石動丸紘宗
• E-mail:ishidoumaruhirotoshi.design@gmail.com