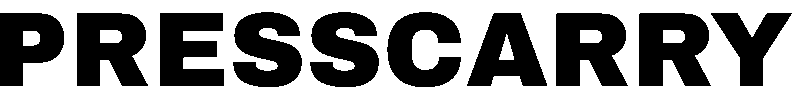提供:@Press

図1. 熱安定性に優れたストロンチウム・ガリウム酸水酸化物と新しいプロトン機能性材料の応用展開
神奈川大学化学生命学部 本橋輝樹教授らの研究グループは、京都大学複合原子力科学研究所 南部雄亮特定教授、近畿大学理工学部 杉本邦久教授、Zi Lang Goo研究員(当時)、九州大学大学院工学研究院 林克郎教授、稲田幹准教授、物質・材料研究機構(NIMS)マテリアル基盤研究センター 木本浩司センター長、豪州原子力科学技術機構(ANSTO)Maxim Avdeev博士との共同研究により、卓越した熱安定性を有するストロンチウム・ガリウム酸水酸化物(注1)を発見しました。本化合物は、独自開発した「気相水酸化物化反応」を用いて合成され、電子顕微鏡、X線回折、中性子回折(注2)、赤外分光(注3)を用いた先端分析により、詳細な結晶構造および高熱安定性に寄与する水素結合(注4)の存在が明らかになりました。本成果により、(酸)水酸化物の開発研究が加速され、燃料電池や固体酸触媒などへ応用可能な革新的プロトン機能性材料の創製に繋がる可能性があります。本研究成果は、2025年8月31日付で米国のアメリカ化学会の専門誌「Inorganic Chemistry」に掲載されました。
【研究成果のポイント】
●卓越した熱安定性を有するストロンチウム・ガリウム酸水酸化物を発見
●電子顕微鏡、中性子回折、赤外分光などを用いた先端分析により、本化合物の結晶構造と化学結合状態を解明
●独自開発した「気相水酸化物化反応」により、プロトン機能性材料の開発研究の加速に期待
【研究の背景】
結晶構造中に水分子から派生した水酸化物イオン(OH-)を内包する金属(酸)水酸化物(一般式MxOy(OH)z)は、多量のプロトン(H+)源を内包する化合物群である。(酸)水酸化物は金属酸化物が水酸化した化合物と見なされ、通常は沈殿法や水熱法(注5)など室温付近の溶液プロセスで合成されることが多く、広く知られた層状水酸化物やペロブスカイト型酸水酸化物以外の未知物質を得るのが困難だった。プロトンが介在する機能性材料には固体酸触媒やプロトン伝導体(注6)など重要なものが多いため、新たな(酸)水酸化物の創製が強く望まれている。当グループは独自開発した「気相水酸化物化反応」を用いて、約700℃まで結晶構造中にOH-を保持できる新規バリウム・インジウム酸水酸化物[Ba2Ox(OH)y]0.55InO2(注7)の合成に成功した。このような熱安定性をもつ酸水酸化物を発見していくことにより、プロトン関連の機能性材料における設計指針の確立と高温応用の新規開拓が期待できる。
【研究の内容】
本研究では、「気相水酸化物化反応(英語では造語”vapor hydroxidation”と命名)」を用いて、新規酸水酸化物Sr2Ga3O6(OH)を発見した(図1)。本合成法では、独自設計した反応装置を用いて金属酸化物を高温・高濃度の水蒸気により直接水酸化物化する。典型的な反応条件は、従来合成法と大きく異なる500℃以上、水蒸気80体積%である。この水蒸気濃度は室温飽和水蒸気の30倍以上(つまり、湿度3000%)であり、高温高濃度水蒸気雰囲気でのみ安定に存在する新材料の発見を狙うことができる。一般に、(酸)水酸化物は300℃程度で水分子を放出するため、500℃以上の高温で物質合成する試みは非常識と見なされ前例がなかったのが重要ポイントである。
電子顕微鏡、X線回折、中性子回折による分析により、Sr2Ga3O6(OH)はストロンチウム(Sr)、ガリウム(Ga)が六角形に配列した構造を有し、内包されたOH-は2つのストロンチウム原子に挟まれた狭い空間に偏在していることが明らかになった。さらに、Sr2Ga3O6(OH)が(酸)水酸化物としては特異的に安定であり、約850℃までOH-を結晶構造中に保持できることが判明した(図1)。詳細な赤外分光測定により、結晶構造中で形成された複数の水素結合が本化合物の熱安定性に寄与していることが示唆された。
【研究の展開】
「気相水酸化物化反応」は新規(酸)水酸化物の探索に極めて有効である。本合成法により高結晶性の生成物が再現性良く得られるため、化学組成と結晶構造について精密なキャラクタリゼーションを行うことができる。実際、当グループは「気相水酸化物化反応」を用いることにより、[Ba2Ox(OH)y]0.55InO2とSr2Ga3O6(OH)を含む数種類の新規酸水酸化物の合成に成功している。この革新的な手法は、従来の(酸)水酸化物合成法と一線を画しており、潜在的なプロトン機能性材料としての(酸)水酸化物の開発、高温環境下でも利用可能な固体酸触媒やプロトン伝導体など革新的プロトン機能性の創製において重要な進展が期待できる。
【掲載論文】
題名 :A Sr-Ga Oxy-Hydroxide with High Thermal Stability: Unraveling Its Characteristic Hydrogen-Bond Network
著者名 :Yusuke Asai, Yuto Nishihara, Yoko Kokubo, Kenji Arai, Kosaku Ohishi, Satoshi Ogawa, Miwa Saito, Yusuke Nambu, Maxim Avdeev, Koji Kimoto, Zi Lang Goo, Kunihisa Sugimoto, Miki Inada, Katsuro Hayashi, *Teruki Motohashi
掲載誌 :Inorganic Chemistry 2025, 64, 18294-18303.
掲載URL :https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5c02586
【謝辞】
本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業 学術変革領域研究(A)「超セラミックス:分子が拓く無機材料のフロンティア」(課題番号JP22H05142、JP22H05143、JP22H05145)、新学術領域研究「複合アニオン化合物の創製と新機能」(課題番号JP16H06440, JP17H05490, JP19H04707)、基盤研究(C)(課題番号JP18K04713, JP25K08282)の支援を受けて行われました。
【用語解説】
(注1)酸水酸化物
同一結晶構造中に酸化物イオン(O2-)と水酸化物イオン(OH-)の両方を内包する複合アニオン化合物の一種。水酸化物イオンは水分子から派生した陰イオンであり、分子イオンを内包した無機材料は「超セラミックス」と呼ばれる。
(注2)中性子回折
結晶構造の分析法。試料からの中性子散乱における干渉効果(回折)を利用して物質中の原子配列を決定する。水素など軽元素の感度が高いため、軽元素を多く含む物質の結晶構造解析に有効である。
(注3)赤外分光
赤外線を用いた分析法。赤外線を物質に照射し、吸収または反射スペクトルを解析することにより、分子イオンなどの化学結合状態を特定することが可能。
(注4)水素結合
酸素など電気陰性度の大きな原子と水素からなる分子や官能基の間に働く化学結合のこと。分子間引力の中では強い相互作用であり、水の特異的に高い沸点や、タンパク質やDNAが立体構造をつくる起源となっている。
(注5)沈殿法、水熱法
(酸)水酸化物の一般的な合成法。沈殿法は、金属塩の水溶液に沈殿剤を加えて金属水酸化物を沈殿として得る手法。水熱法は、高温高圧の熱水の存在下で行う合成法。
(注6)固体酸触媒、プロトン伝導体
いずれもプロトン(H+)が介在する機能性材料。固体酸触媒とは、プロトンが固体表面に酸性点(プロトンを供与する部位)をもち、それを利用して化学反応を促進する触媒材料。プロトン伝導体とは固体電解質の一種であり、プロトンが電荷キャリアである固体物質。低温~中温域で動作する燃料電池への応用が期待されている。
(注7)新規バリウム・インジウム酸水酸化物[Ba2Ox(OH)y]0.55InO2
「気相水酸化物化反応」により発見した新規構造をもつ酸水酸化物。熱安定性に優れており、500℃付近でプロトン伝導性を有する。掲載論文:”Thermally stable proton-conducting oxy-hydroxides synthesized in concentrated water vapor,” Journal of Materials Chemistry A 2025, 13, 21472-21479.
【関連リンク】
理工学部 理学科 教授 杉本邦久(スギモトクニヒサ)
https://www.kindai.ac.jp/meikan/2743-sugimoto-kunihisa.html
理工学部
https://www.kindai.ac.jp/science-engineering/