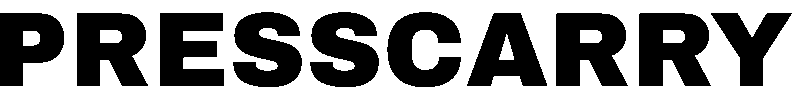提供:@Press

サヴァケファレの等身大化石レプリカの頭部を手にする高崎助教
頭の骨が分厚く頑丈なドーム状になっていることから、「頭突き恐竜」と呼ばれるパキケファロサウルス類の白亜紀前期(約1億1000万年前)という最古の化石がモンゴルで見つかり、岡山理科大学恐竜学科の高崎竜司助教らの研究グループは新属新種の「ザヴァケファレ・リンポチェ」と命名しました。保存状態も良く、研究グループはパキケファロサウルス類の生態や進化の過程解明につながる極めて重要な発見としています。研究成果は9月18日、英科学誌「ネイチャー」電子版に掲載されました。
研究グループは高崎助教のほか、米国ノースカロライナ州立大学兼モンゴル古生物学研究所のチンゾリグ・ツォクトバートル博士、福島県立博物館の吉田純輝学芸員ら。
岡山理科大学で記者会見した高崎助教によると、この化石は2019年、モンゴル・ゴビ砂漠の白亜紀前期の地層から、特徴的な頭部をはじめ手足、胴体など全身の骨格を発見。胃の中には鳥などが咀嚼に使う「胃石」もありました。
英科学誌「ネイチャー」電子版 : https://www.nature.com/articles/s41586-025-09213-6
「世界初」づくしの発見!「ネイチャー」に掲載
パキケファロサウルス類では「世界初」づくしの発見で、「白亜紀前期」という最古の時代をはじめ「手の指」や「胃石」、「完全な尻尾」が見つかったうえ、「年齢推定」まで可能でした。
研究グループが脚の骨を薄く切り出して、木の年輪のような成長線を調べたところ、2歳以上の若い個体だったことが判明。体重は約6㌔、体長は1㍍と推定しています。
これまで北米、アジアで見つかっているパキケファロサウルス類の化石は、ほぼ全てが中生代末期(約8000万年前~6600万年前)のもので、ほとんどが頭部のみ。このため他の恐竜類に比べて、その姿や生活の様子、分類や成長パターン、運動能力などが不明の「謎の恐竜グループ」とされていました。
研究グループは①上あごの骨の表面が滑らか②特殊な頭骨の構成③後頭部のデコボコがない④下顎の最前列の歯が小さい⑤尻尾の腱の形が特殊――というこれまでのパキケファロサウルス類にない特徴から新属新種と判断しました。
「ザヴァケファレ」は、チベット語で「根」「起源」を意味する「ザヴァ」と、ラテン語で「頭」を意味する「ケファレ」を組み合わせ、「リンポチェ」はチベット語で「尊きもの」で、「ドーム頭の恐竜の起源にして尊い宝」という意味です。
今回発見されたザヴァケファレによって、頭部ドームは従来考えられていたより1400万年以上前から存在していたことが分かりました。ザヴァケファレは後の時代のパキケファロサウルス類に比べて後頭部の構造が発達していないという原始的な特徴を持っており、ドームは進化の初期段階で前方から膨らんでいき、その後、後方がドーム化していくという過程を経て形成されていくことが初めて確認されました。
また、発見されたザヴァケファレは、頭部ドームがしっかり発達していたにもかかわらず未成熟な個体で、体全体が成熟し切る前から闘争などでドームを機能させていたとみられ、「社会行動の進化を探るうえでも大きな手掛かりになる」としています。今後、歯の分析などから、どのようなものを食べていたかも明らかになってくる、と研究グループは期待しています。
高崎助教は「素晴らしい研究に関われて光栄です。ザヴァケファレにはまだまだ解明すべき謎がたくさん残っているので、今後の研究が楽しみです」と話しています。
恐竜学博物館で全身骨格レプリカを展示
ザヴァケファレの全身骨格レプリカは9月18日(木)から10月19日(日)まで、岡山理科大学C2号館1階の恐竜学博物館で一般公開されます。

実物の化石の側面(左)と上面(右)=研究グループ提供

ザヴァケファレの産出現場=研究グループ提供

ザヴァケファレの全身骨格=研究グループ提供

脚の断面写真=研究グループ提供

ザヴァケファレ同士の頭突き行動を描いた復元画(©服部雅人)

ザヴァケファレの復元骨格図=白色が発見部位=(©増川玄哉)

記者会見風景

会見する高崎助教(左)と實吉玄貴・恐竜学科教授(右)

ザヴァケファレの実物大化石のレプリカを手に報道関係者に解説する高崎助教(右)

恐竜学博物館で一般公開が始まったザヴァケファレの全身骨格レプリカ
岡山理科大学 : https://www.ous.ac.jp/